なぜなぜ分析が苦手な人はなぜ多い?なぜなぜ分析の裏に隠れた3つの思考法【ものづくりは人づくり~カイゼン人材を育てよう~⑦】
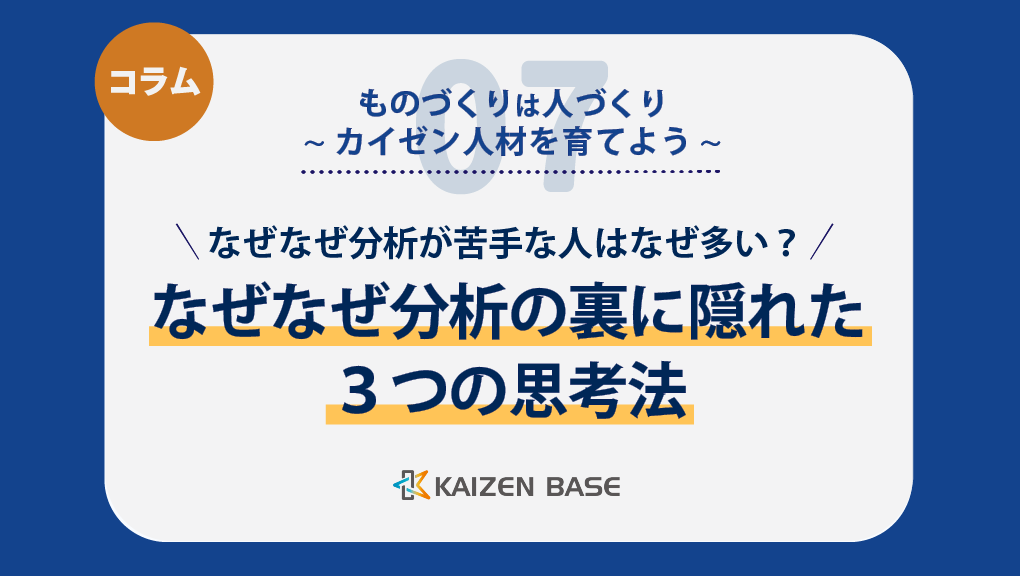
.png)

どうして難しい?なぜなぜ分析
本日は、製造業では避けて通ることができない「なぜなぜ分析」についてお話しさせていただきます。
なぜなぜ分析とは、問題をただ処置するだけではなく、「なぜ」を繰り返して問題を深堀して、根本原因を対策することで再発を防ぐ考え方のことです。もともとトヨタ自動車の問題解決の考え方から生まれたもので、今では世界的に活用されている分析手法です。製造業では、日々の業務や改善活動で欠かせない問題解決の技術ですが、なぜなぜ分析に苦手意識を持っている方も多いと思います。
なぜなぜ分析の難しいところは、単純に「なぜ」を繰り返すだけではなく、真因を特定するために複数の観点からの多角的に物事にアプローチする思考が必要となる点です。本日は、なぜなぜ分析の裏に隠れた3つの思考法をご紹介します。
なぜなぜ分析と各思考法の関係
前述のとおり、なぜなぜ分析は、問題の根本原因を特定するために「なぜ」を繰り返し問いかける手法です。「なぜ」を繰り返すとだけ聞くとなんだか簡単そうに聞こえますが、実はそのプロセスの中では
・ロジカルシンキング(論理的思考)
・ラテラルシンキング(水平思考)
・クリティカルシンキング(批判的思考)
の3つの思考法が重要な役割を果たしているのです。
ロジカルシンキング(論理的思考)
ロジカルシンキングは、問題を体系的に分析し、原因と結果の関係を明確にするための方法です。これは、問題を細かく分解し、各要素の関係性を明確にすることで、問題の本質を理解しやすくします。例えば、ある製品の不具合が発生した場合、その原因を特定するために、製造プロセスや使用材料、設計などを詳細に調査します。信頼性の高い解決策を見つけるために、主観や感情に左右されないデータや事実に基づいて結論を導くことがロジカルシンキングには求められます。
ラテラルシンキング(水平思考)
ラテラルシンキングは、既存の枠にとらわれずに新しい視点から問題を解決する方法です。従来の方法では見つけられない解決策にたどり着くための柔軟な思考法です。固定観念にとらわれず、多角的な視点から問題を捉えることで、革新的なアイデアを生み出すことができます。慣習やルール、前提条件にとらわれない自由な発想が求められる思考法です。
クリティカルシンキング(批判的思考)
クリティカルシンキングは、情報を批判的に評価し、偏見や誤りを排除するための方法です。例えば、「情報は本当に正しいのか?」「自分に都合の良い考えに偏っていないか?」等、自らに問いを投げかけ、自分の考えに対して懐疑的な思考(クリティカルマインド)を持つこともクリティカルシンキングでは重要になります。
なぜなぜ分析と各思考法の関係
なぜなぜ分析には、これら3つの思考がバランスよく求められます。
まず、ロジカルシンキングを用いることで、問題を体系的に分析し、各「なぜ」の背後にある原因を論理的に追求します。これにより、問題の構造を明確にし、根本原因を特定するための基盤を築きます。
次に、ラテラルシンキングを取り入れることで、固定観念にとらわれず、多角的な視点から「なぜ」を問いかけることができます。これにより、従来の方法では見つけられなかった原因を発見し、新しい解決策を考案することができます。
最後に、クリティカルシンキングを活用して、得られた情報や仮説を批判的に検討し、バイアスや誤りを排除します。これにより、感情や個人的な意見を排除し、客観的に原因を特定することができるのです。
なぜなぜ分析ができると
これらのシンキング系の全ての要素を合わせた実践的思考がなぜなぜ分析だということが分かると、難しいと感じる方が多いのも納得いただけると思います。なぜなぜ分析は、3つの思考法を駆使して解決策を導くプロセスとも言い換えることができるのです。
このようなお話しをすると余計になぜなぜ分析に対して苦手意識を持たれてしまいそうですが、断言できるのは、「なぜなぜ分析がどのくらいできるか」は「仕事がどのくらいできるか」とほぼイコールだということです。
原理原則を考える力、仮説を立てて検証する力、データを使って説得する力、情報を整理する力、結論づける力・・・等々。仕事を進める上で重要なスキルがまんべんなく盛り込まれているのがなぜなぜ分析なのです。できるビジネスパーソンを目指すために、まずはなぜなぜ分析、その裏に隠れた思考力に着目してみるのもよいかもしれません。
次の記事を読む
間接部門でも業務改善!属人化から脱却しよう【ものづくりは人づくり~カイゼン人材を育てよう~⑧】
前の記事を読む
製造業のマネジメント人材に求められるスキルとは【ものづくりは人づくり~カイゼン人材を育てよう~⑥】
カイゼンについて学ぶ!学習コースのご紹介
カイゼンベースの学習コースでは、カイゼンに関する具体的な内容を動画や理解度テストにより学習することが可能です。詳細の学習や実践でのご活用をご検討の方は、是非ご活用ください。
学習コース「k1-01:アニメで学ぶカイゼン活動」
トヨタ生産方式は、今や生産活動の基本中の基本と言ってよい存在です。本講座では、トヨタ生産方式の2本柱である「ジャストインタイム」や「ニンベンの付いた自働化」をはじめとした、トヨタ生産方式の基礎知識をアニメーションで分かりやすく学習します。
学習コースの詳細
Lesson1:世界中で取り組まれる“カイゼン”(7:02)
Lesson2:カイゼンは誰のため?(8:13)
Lesson3:カイゼンの2種類のアプローチ(8:53)
Lesson4:三現主義、5ゲン主義とは(7:16)
Lesson5:ものづくりの3要素「QCD」とは(10:00)
Lesson6:PDCAサイクルとは(6:25)
Lesson7:トップダウンとボトムアップ活動(8:14)
Lesson8:カイゼンマインドを育てる4つの“機会”(7:35)
「Lesson1:世界中で取り組まれる“カイゼン”」の動画はどなたでもご視聴頂けます。
「Lesson2:カイゼンは誰のため?」の動画は無料会員登録を行うことでご視聴が可能になります。
資料請求はこちらから
サービス紹介資料・価格表を無料でダウンロードできます。お気軽にお問い合わせください。
関連コラム
-
理解が深まる社内教材の作り方【ものづくりは人づくり~カイゼン人材を育てよう~⑫】
MORE -
教材制作のポイント「わかりやすい」の正体とは?【ものづくりは人づくり~カイゼン人材を育てよう~⑪】
MORE -
管理職が知っておくべきヒューマンエラーの本質【ものづくりは人づくり~カイゼン人材を育てよう~⑩】
MORE -
職場全体でカイゼン文化を根付かせよう【ものづくりは人づくり~カイゼン人材を育てよう~⑨】
MORE -
間接部門でも業務改善!属人化から脱却しよう【ものづくりは人づくり~カイゼン人材を育てよう~⑧】
MORE -
製造業のマネジメント人材に求められるスキルとは【ものづくりは人づくり~カイゼン人材を育てよう~⑥】
MORE
.png)








